育児&幼児教育サポーターのUmiです😊
「叱らない育児」と聞くと、
「甘やかしてしまうのでは?」とか
「言うことを聞かなくなりそう…」
と不安になる方も多いかもしれません。
でも、叱らない=放任という意味ではありません。
むしろ叱らずに、子どもの心にちゃんと届く伝え方をすることで、
子どもは自分で考えて行動できるようになるのです。
私がオーストラリアで幼児教育を学んだときに印象的だったのが
「子どもに“NO”や“Don’t do that(それしないで)”を使わないようにしましょう」
という教えでした。
えっ、危ないことをしていたら止めないの?と思いますよね。
でも、そこには子どもの脳の発達や感情の反応をふまえた理由があるのです。
♦︎ポイントは「最初の一言を飲み込むこと」
これは、私が授業で教わってとても印象に残っている言葉です。
つい「えっ!何してるの!?」「ダメでしょ!」と口に出しそうになるけれど、
その最初の一言をグッとこらえて、行動を導く言葉に変える。
これが、「叱らない育児」の本質だと思います。
♦︎「NO!」だけが記憶に残る子どもの脳
たとえば、こんな場面を想像してみてください。
子どもが椅子の上に立っています。
思わず「こら!ダメって言ったでしょ!降りなさい!」と言ってしまいそうになりますよね。
でもそのとき、子どもが受け取るのは
「怒られた」「怖かった」という感情のインパクトだけ。
大人が伝えたかった
「椅子の上は危ない」「降りてほしい」
という本当に大切なメッセージは、
その後に続いていたとしても、頭に入らなくなってしまうのです。
だからこそ、最初の“怒りの一言”は飲み込んで、
シンプルに行動を導く言葉に変える。
♦︎たとえば、こんなふうに
椅子の上に立っていたら…
✕「こら!ダメって言ったでしょ!降りなさい!」
◎「椅子は座るところだよ。足は床に降ろそうね。」
お水をこぼしてしまったら…
✕「何してるの!もう!」
◎「タオルを持ってきて拭こうか。」
「怒られるからやめる」ではなく、
「危ないからやめる」「どうしたらいいかを自分で分かっている」に変えていく。
そんなふうに伝えていくと、
子どもは少しずつ、自分で考えて行動できるようになります。
♦︎子どもは「怒られて育つ」のではなく、「理解して育つ」
私が子どもたちと関わってきて感じたのは、
子どもたちは、ちゃんと分かる力を持っているということ。
その力を引き出すためには、大人が一方的にコントロールするのではなく、
「伝える」→「理解する」→「行動が変わる」というプロセスを、
ていねいに繰り返していくことがとても大事なんです。
叱らずに伝えるって、最初は難しいけれど、
少しずつ慣れてくると、子どもとの関係性もグッと穏やかになります。
子どもにとって大事なのは「失敗=怒られること」ではなく、
「失敗してもどうすればいいか知っている」という安心感です。
その安心感があると、子どもはチャレンジする力が育ち、
失敗しても立ち直る力(レジリエンス)も育まれます。
そしてそれは、大人が怒りではなく、解決のヒントを渡してきたからこそ育つ力なんです。
♦︎完璧じゃなくていい
私たちも人間なので、毎回冷静に対応できるわけではありません。
でも、つい出そうになるその一言をグッと飲み込んで、別の言葉に変えること。
それを少しずつ習慣にしていくと、
大人たちも子どもたちも、お互いにラクになっていきます。
叱らない育児は、ただ優しくする育児ではないと思います。
叱らない育児は、子どもの心に届く、愛ある関わり方です。
完璧を目指さなくて大丈夫。
できるときに、できるだけ。
その一歩が、お子さんの未来にしっかりつながってゆくはずです🌱
今日もみんなが笑顔で過ごせて
穏やかに熟睡できますように🩵

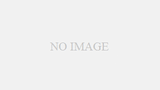
コメント