こんにちは、育児&幼児教育サポーターのUmiです😊
子育てをしていると、ふと「この子はちゃんと自信を持って育っているだろうか」と、心配になる瞬間ってありませんか?
集団の中にいるとき、他の子よりも引っ込み思案に見えたり、逆に無理して元気に振る舞っているように感じたり…
私自身、保育や育児の現場で何度もそんな場面に出会う中で気づいたことは、
子どもたちが“自分らしさ”を発揮できるかどうかは、「自分はここにいていいんだ」と思えるかどうかにかかっていること。
今回は、マズローの「欲求5段階説」の第3段階「所属と愛の欲求」と、EYLF(オーストラリアの幼児教育指針)のOutcome 1「Children have a strong sense of identity」とのつながりについて、少し深く探ってみたいと思います。
♦︎愛され、受け入れられることが「自分らしさ」の土台になる
マズローは、人間が「誰かに受け入れられ、愛されている」と感じることで、初めて“安心して自分らしくいられる”と考えました。
この「所属と愛の欲求」は、家族や仲間、コミュニティとのつながりを通して満たされていくものです。
でも、つながりとは「ただそこに一緒にいる」だけでは生まれません。
「あなたがいてくれてうれしいよ」「ここにいて大丈夫だよ」という、存在を歓迎する空気があってこそ、子どもは「自分はここにいていいんだ」と感じるのだと思います。
自己肯定感、意欲、他者との関係性——
すべての土台になるのが、この“受け入れられている感覚”です。
それがあれば、子どもたちは自分を信じ、他者とも関わり、自ら育っていく力を発揮できるようになるのではないでしょうか。
♦︎EYLFのOutcome 1:子どもが「自分らしさ」を感じられる保育
オーストラリアのEYLF(Early Years Learning Framework)では、Outcome 1の中でこう語られています:
Children feel safe, secure, and supported.
→ 子どもが「安心・安全に守られ、支えられている」と感じること。
Children develop their emerging autonomy, inter-dependence, resilience and sense of agency.
→ 子どもが「自分で考え、自分で動ける」力や、他者とつながる力、そして折れない心を育むこと。
ここで大切なのは、安心感と自立心は、セットで育つという視点👀
「守られている」と感じているからこそ、子どもは新しいことに挑戦しようと思えるのです。
EYLFでは、「子どもがどのように自分自身を認識しているか」が、その子の学びの質や深さに関係しているとされています。
だからこそ、“あなたはあなたでいい”というメッセージが、日々の保育の中に自然に込められていることがとても大切なのです。
♦︎保育の現場でできること:子どもに“Welcome”を伝える関わり
私がオーストラリアの保育園で学んだことのひとつに、「子どもが“ここにいていいんだ”と感じられるような関わり」を意識するという姿勢がありました。
それは特別な技術ではなく、日々の小さな行動の積み重ねです:
- 朝、名前を呼んで笑顔で迎える
- 子どもの表情や仕草の小さな変化に気づき、すぐに声をかける
- 文化的・言語的背景を尊重し、違いを大切にする姿勢を見せる
- 子どもの家庭文化や経験を、園での活動にも自然に取り入れる
たとえば、英語が母語でない子が、緊張して登園してきた朝。
その子の母国語で「おはよう」と言ってあげるだけで、ふっと顔がほころぶことがあります☺️
「あなたのことをちゃんと見てるよ」
「あなたの存在を大切に思ってるよ」
そんなまなざしが、子どもの心に安心の根を伸ばしていくのだと思います🌱
♦︎つながりの中で、子どもは自分を見つける
子どもが“自分らしさ”を発揮するには、「何かができるようになる」よりも前に、
「ここにいるだけでいい」「自分のままでいい」と感じられる環境が必要です。
マズローの“所属と愛の欲求”と、
EYLFが大切にする“アイデンティティの確立”は、
どちらもそのことを、別の言葉で私たちに教えてくれているのだと思います。
大人の関わりひとつで、子どもは安心し、自信を持ち、社会とつながる準備を始めます。
そしてその姿を見て、私たち自身もまた「人とつながるあたたかさ」に気づかされたりします。
子どもたちが少しでも「ありのままの自分」でいられる毎日を、私たち大人がつくっていけたらいいな🌿
今日もみんなが笑顔で過ごせて
穏やかに熟睡できますように🩵

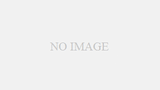
コメント