育児&幼児教育サポーターのUmiです😊
前回は、マズローの「人間の欲求5段階説」とオーストラリアの幼児教育(EYLF)には重なる視点がある、というお話をしました。
今回はその中でも、最も基盤となる 「生理的欲求」と「安全の欲求」について深掘りしていきます🌱
♦︎生きるために必要な「土台」が満たされているか?
マズローのピラミッドの一番下にあるのが「生理的欲求」。
食事・睡眠・排泄・休息など、生きるために欠かせない身体的なニーズのことですね。
そしてその上にある「安全の欲求」は、安心・安定・予測可能性といった“心の土台”に関わる部分。
この2つが不安定だと、子どもはその上にある“学び”や“社会性”にエネルギーを向けることができません。
♦︎EYLF Outcome 3:心と身体の健康を支える環境づくり
EYLF(Early Years Learning Framework)のOutcome 3は、まさにこの「生理的欲求・安全の欲求」と深くつながっています。
Outcome 3のゴールは、子どもたちが:
- 自分の身体や健康について知る
- 健康で安全な生活習慣を身につける
- 快適さや心地よさを感じる力を育む
- 安全な環境の中で安心して自己表現する
という経験を通して、自分の「健やかさ」や「安心」を感じられるようになること。
これって、単に“怪我をさせない”とか“お昼寝させる”という話ではなく、
「自分は守られている」「心地よくいられる」という感覚を、日常の中で積み重ねていくということなのです。
♦︎大切なのは、“してあげる”より“気づけるように支える”
たとえば、保育の現場でよく大事にされるのが:
「泣いてから動くのではなく、泣く前のサインに気づいて整えておく」
という視点。
お腹が空いていないか、眠くなってきていないか、排泄のタイミングではないか。
子どもが自分では言葉にできない状態を、保育者が観察し、予測し、必要なサポートを届けること。
でも、それと同時にEYLFでは、子ども自身が「今の自分」に気づき、整える力を育てることも大切だとされています。
「なんだか疲れたな」
「ちょっと横になりたいな」
「お水飲んだ方がよさそう」
そんなふうに、自分の身体の声を聞く力。
それを、安心できる環境の中で育んでいくことが、EYLFのOutcome 3の大きなポイントなんです。
♦︎まずは「ここは安心していられる場所」と感じてもらうことから
子どもにとって、「この場所は安心できる」「私は大切にされている」と感じることができれば、
初めてその先の社会的な関わりや、学びに向かう土台が整います。
だからこそ、EYLFでは“Belonging(安心して居られること)”が最も大切な価値観とされているのです。
保育者が子どもを守る存在であると同時に、
子ども自身が“自分の快・不快を認識してケアできる存在”へと育っていく。
それを支えるのが、私たち大人の「見守る力」と「環境づくりの工夫」なのです。
マズローの理論とEYLFを照らし合わせてみると、「人が育つとはどういうことか?」を改めて見直すきっかけになります。
次回は「社会的欲求(愛と所属)」にフォーカスして、
EYLFのBelongingや人間関係にどうつながっているかをお届けします✨
今日もみんなが笑顔で過ごせて
穏やかに熟睡できますように🩵

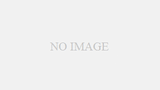
コメント