育児&幼児教育サポーターのUmiです😊
「子どもは教えなければ学ばない」
そう思っていませんか?
でも実はその逆で、子どもは“教えすぎない方”が深く学び、自分で育っていく力を持っているのです。
今回は、私がオーストラリアの保育現場で学んだ「信じて見守る保育」について、Play based learningの考え方を交えながらお伝えします。
♦︎ 子どもには“育つ力”が備わっている
私たち大人はつい「こうした方がいいよ」「こうすればうまくいくよ」とアドバイスしたくなりますよね。
でも、子どもは自分自身の体験や失敗、発見を通してこそ、本当の意味で「学ぶ」ことができます。
🌱 例えば──
砂遊びで水の流れを工夫する中で「川ってこうやってできるんだ」と気づいたり、
友達とのケンカから「自分の気持ちも、相手の気持ちも大切なんだ」と学んだり。
この“育ち”のプロセスは、大人が用意した正解の中では得られにくい学び。
♦︎教えすぎは「自分で考える力」を奪ってしまう
「こうしようね」「これが正解だよ」と言われ続けた子どもは、
いつしか「自分で考えなくていい」というクセを身につけてしまいます。
すると──
- 失敗を怖がるようになる
- 正解がない場面で動けなくなる
- 自己肯定感が育ちにくくなる
という悪循環に…。
“教える”のではなく、“考えるきっかけを与える”ことが大切なのです。
♦︎「自分で決めていいんだ」は、人生の土台になる
オーストラリアの保育では、子どもにできるだけ選択肢を与えていました。
🟡 今日は何で遊ぶ?
🟡 おやつを食べる前に何をする?
🟡 このトラブル、どうやって解決したい?
こうした日々の小さな選択が、「自分のことを自分で決めていい」という感覚を育て、
やがてそれは自信・責任感・自己肯定感につながっていきます。
♦︎大人の「手放す勇気」が、子どもを伸ばす
「手伝った方が早い」
「言った方がわかる」
そう思うこと、ありますよね。
でも!ちょっとだけ時間をかけて、子どもが自分でやってみるのを見守ると、
思いがけない発見や成長が見られることも。
例えば:
✅ 靴をはくのに時間がかかっても、自分でできた時の達成感は格別!
✅ トラブルで困っていても、子ども同士で解決する力が育つチャンス!
「待つ・信じる・見守る」この3つが、子どもの育ちを支える大きな柱になっていきます。
♦︎教えなくても、環境は整えてあげられる
「何もしない」と「見守る」は違います。
Play based learningでは、子どもが自ら関われるように、大人が環境を整えることが重要とされています。
✔️ 子どもが自由に選べる素材や遊びのスペース
✔️ 興味関心を深められる図鑑や道具
✔️ 安心して試せる「失敗しても大丈夫」な空気
大人が“教える”代わりに、“環境をデザイン”することで、子どもは自然に学びに向かっていきます。
♦︎信じて見守る。それが一番の教育
子どもたちは、自分のペースで、自分なりに世界と向き合いながら成長していきます。
✅ 答えを与えるより、「どうしたい?」と問いかける
✅ ゴールを決めるより、「何を感じた?」に耳を傾ける
✅ 指示するより、「どこまでできたね!」と認める
そうやって子ども自身が自分の人生を選び取る力を育てていく保育・育児こそ、
これからの時代に必要とされる教育ではないかと感じています✨
今日もみんなが笑顔で過ごせて
穏やかに熟睡できますように🩵

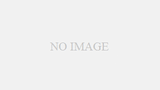
コメント