育児&幼児教育サポーターのUmiです😊
♦︎子どもの学びを見逃さない“まなざし”とは?
「子どもは遊ぶのが仕事」と言われるように、遊びの中にはさまざまな学びの要素が詰まっています。
オーストラリアの幼児教育で大切にされている“Play based learning(遊びを通した学び)”でも、子どもの遊びを観察する力が保育者にとってとても重要なカギになります。
今回は、私が現地で学び、実践の中で大きく変わった「観察の視点」についてご紹介します。
♦︎「ただ遊んでるように見える」から抜け出す
たとえば、子どもが積み木を何度も何度も崩している場面。
大人から見ると「壊してばっかり」「ふざけてる」と感じてしまうかもしれません。
でも、よく観察してみるとその子は、
「どの高さで倒れるのか?」
「どの角度から崩すとどうなるか?」
といった因果関係や物理的な感覚を試しているのかもしれません。
つまり、子どもの行動の“背景にある学び”を見る視点があるかどうかで、関わり方も大きく変わってくるのです。
♦︎観察する=評価することではない
ここで大切なのは、“観察とは「評価」ではなく、「気づき」や「理解」である” ということ。
「この子は〇〇ができる・できない」と判断するのではなく、
- 今、何に興味を持っているのか?
- どんな表情や声で遊んでいるか?
- 誰と、どんな関わりをしているか?
- 同じ遊びをどんな風に繰り返しているか?
といった小さなサインを拾いながら、その子の「今ここ」に寄り添うことが大切です。
♦︎遊びの中に隠れている「発達のサイン」を見つけよう
オーストラリアの保育では、日々の観察をもとに「今、この子は何を学んでいるのか?」を記録に残し、カリキュラムに反映させます。
たとえば:
- 粘土遊びで同じ形を何度も作る → 反復行動からの達成感や創造力
- ごっこ遊びで役割分担をする → 社会性・言語力の発達
- ジャンプやバランス遊びに夢中 → 身体機能の発達の段階
こうした行動は、子どもからの「発達のサイン」。
見逃さずキャッチできる目を育てていくことが、保育者の大事な役割なのです。
♦︎まずは「何もしないで見てみる」ことから
とはいえ、「よし、観察しよう!」と思うとついメモをとったり、評価しようと力が入ってしまいがち。
でも、最初の一歩はもっとシンプルでOKです。
▶️ そっと近くに座って、黙って見てみる。
▶️ 子どもの表情、目線、手の動き、言葉に注目する。
▶️ 「へえ、こんなことに夢中なんだ」と心の中でつぶやく。
これだけで、今まで見えていなかった“子どもたちの世界”がグッと近く感じられるはずです。
♦︎観察力がつくと、保育がもっと楽しくなる
子どもの遊びの中にある「学びの芽」を見つけられるようになると、保育がどんどんおもしろくなってきます。
「この子、こんなこと考えてたんだ!」
「昨日まではできなかったのに、今日できた!」
そんな発見があると、大人の方もワクワクしてしまいますよね♪
そしてその気づきが、次の関わり方や環境づくりにもつながっていくのです。
♦︎日々送られている子どもたちからのメッセージ
子どもたちは言葉では言わなくても、「今、これがしたい」「これが気になる」というサインを毎日出しています。
(たとえそれが一見、不思議だったり困った行動だとしても…😅)
それを受け取れるかどうかは、大人の観察力次第。
「遊んでいる姿」こそが、子どもたちの学びの真っ最中。
その小さなドラマに気づけるようになると、保育はもっと豊かで楽しい時間になるのではないでしょうか☺️
今日もみんなが笑顔で過ごせて
穏やかに熟睡できますように🩵

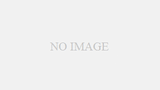
コメント