育児&幼児教育サポーターのUmiです😊
♦︎声かけひとつで、遊びはぐっと深まる
前回の記事では、「子どもの遊びを観察する力」の大切さについてお伝えしました。
子どもたちは遊びの中で、今の興味や成長段階に合ったことを自ら選び、試し、まるでスポンジのように吸収しています。
今回はその「観察」から一歩進んで、保育者や大人がどう関わることで、遊びの中の“学びの芽”をより豊かに育てられるかについてシェアさせていただきます。
♦︎子どもはすでに「学びの真っ最中」
まず大前提として覚えておきたいのは、
大人が何かを“教えなければ”学ばないわけではないということ。
たとえば、ただ泥だんごを作っているように見える子どもも、
・どんな固さなら形が保てる?
・水はどのくらい必要?
・もっと丸くするにはどうする?
…といったことを自分なりに試行錯誤しています。
保育者がやるべきことは、「こうやって作るんだよ」と答えを与えることではなく、
その探求がより深まるように、問いかけたり、環境を用意したりすることです。
♦︎ 魔法の声かけ:「やめなさい」ではなく「どうしたい?」
オーストラリアの保育現場で私が学んだのは、肯定的な言葉で関わることの大切さです。
たとえば、
子どもが大量の水をバケツからこぼして遊んでいる場面。
🙅♀️「ダメでしょ、水をそんなに使っちゃ!」
ではなく、
🙆♀️「面白いね!どんなふうに流れていくか見てみる?」
🙆♀️「他の子も使いたいときは、どうしたらいいかな?」
こうした声かけは、子どもの意欲を削がずに、思考を促す関わりになります。
その結果、子どもは「もっと考えたい」「やってみたい」という気持ちを持ちながら、社会性・協調性・創造性といったさまざまな力を育てていきます。
♦︎ 見守るだけでなく「ちょっとだけヒントを出す」
Play based learningでは、「自由に遊ばせる」だけでなく、子どもの思考が広がる“きっかけ”を与えることも重要です。
たとえば、積み木で高く積もうとして何度も倒れている子がいたら:
💡「どんな形だと倒れにくいと思う?」
💡「これは土台に使えそうかな?」
💡「一緒に考えてみようか?」
こうした小さなヒントや提案を通じて、子どもは自分で試し、気づき、学ぶ喜びを感じることができます。
これは、単なる「教える」とは違う、学びを“育てる”関わりです。
♦︎ あえて“手を出さない”選択も大切
ときには、「助けてあげた方がいいかな?」と思う場面でも、あえて見守る勇気が必要です。
子どもが挑戦しているとき、大人がすぐに正解を示すと、「失敗しても誰かが助けてくれる」と思ってしまったり、自信を失ったりすることがあります。
「どうするのかな?」と少し距離をとって見守ることで、
・考える時間
・工夫するチャンス
・達成感を得る機会
が生まれます。
♦︎ 遊びが“ただの遊び”で終わらない関わりとは?
遊びを学びにつなげる関わりには、いくつかのコツがあります:
✅ 子どもの「今やってること」に関心を持つ
✅ 否定するのではなく、問いかけて考えを引き出す
✅ 「何を学べるか?」という視点で環境や道具を選ぶ
✅ 結果よりも、プロセス(やりとり・試行錯誤)を大事にする
これらを意識するだけで、遊びの質がぐーんと深まり、子どもも大人も学びの時間を楽しめるようになります。
♦︎あなたの一言が、子どもの未来を広げる
子どもたちは、遊びの中で世界を知り、自分を知り、他人を知っていきます。
大人の何気ない声かけや関わり方によって、その旅路を豊かなものにサポートできます。
「こうしなさい」ではなく、「どうしたい?」
「それはダメ」ではなく、「こうするとどうなる?」
そんな関わりのひとつひとつが、子どもの中に小さな“学びの芽”を育てていくのです。
▶️次回の記事では、「教えなくても育つって本当?」というテーマで、子どもの自主性や自己肯定感を育てる保育の考え方をご紹介します。
お楽しみに♪
今日もみんなが笑顔で過ごせて
穏やかに熟睡できますように🩵

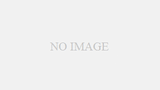
コメント