育児&幼児教育サポーターのUmiです😊
「子どもの力を伸ばすには、何を教えたらいいんだろう?」
そんな悩みを持つ大人たちは少なくないのではないでしょうか。
でも、子どもの学びや育ちに大きな影響を与えているのは、「教え方」だけではありません。
それ以上に大切なのが、子どもが日々を過ごす“環境”かもしれません。
オーストラリアの幼児教育で使われる考え方に、こんな言葉があります。
“The environment as the third teacher”
「環境は第3の教師」
これは、子どもにとって
- 第1の教師は 親や家庭
- 第2の教師は 保育者や教師
- そして第3の教師は 環境そのものである、という考え方です。
今回は、この「環境が子どもを育てる」という視点から、Play based learningの中でどのように環境を整えていけるかを具体的にお伝えします。
♦︎子どもは環境から“無言のメッセージ”を受け取っている
子どもたちは、言葉だけでなく、目の前の空間・道具・レイアウト・雰囲気からもたくさんの情報を感じ取っています。
たとえば──
✅ おもちゃが整然と並んでいる → 丁寧に扱おうという気持ち
✅ 本が手に取りやすい高さにある → 読書への興味
✅ 複数の素材が自由に置かれている → 自分で選び、創造する自由
環境は、子どもに「どんな行動をしていいか」「どう関わっていいか」を静かに伝える役割を果たしているのです。
♦︎オーストラリア保育の環境づくり:5つの特徴
私がオーストラリアの保育現場で見た、環境づくりのポイントをご紹介します。
1. オープンエンドの素材が多い
👉 積み木、布、木の実、段ボール、石など、正解のない素材を用意することで、子どもの想像力と創造力を刺激します。
2. “自分で選べる”仕組み
👉 本棚・おもちゃ棚はすべて子どもの目線に。いつでも、どれを選んでもいいという自由が、自主性を育てます。
3. インドアとアウトドアの “つながり” を意識する
👉 外遊びの素材を室内に取り入れたり、窓から自然が見える配置にするなど、内と外がゆるやかにつながっていることで、環境が自然や季節を語りかけるような空間になる。
4. ドキュメンテーションで “見える化”
👉 子どもの作品や活動の写真が壁に貼られ、「あなたの学びを大切にしているよ」というメッセージになります。
5. 静と動のスペースがある
👉 にぎやかに遊べる場所と、静かに過ごせるスペースがバランスよく配置され、気持ちを整える習慣も育ちます。
♦︎日本の家庭や園でもできる!環境の整え方アイディア
「そんな大きな園じゃないから無理…」と思うかもしれませんが、小さな工夫でも大きな変化が生まれます。
🟡 棚の高さを見直してみる(子どもの目線で)
🟡 素材の種類を増やす(“遊び方が決まっていない”ものを)
🟡 その日の遊びを、写真や言葉で “見える化” して貼ってみる
🟡 静かに過ごせる「読書コーナー」や「ひとりの空間」をつくる
これだけでも、「ここは私の居場所だ」と子どもが感じられる空間ができていきます。
♦︎環境が変わると、子どもの行動も変わる
私自身、オーストラリアで保育の現場に立ち、
- 乱暴だった子が、素材を変えただけで穏やかに集中するようになったり
- 発言が少なかった子が、環境から刺激を受けて、自分から行動するようになったり
という場面を何度も目にしました。
環境は、子どもの “ありたい姿” を自然に引き出してくれる力を持っています。
♦︎もうすでに “できていること” に目を向けてみよう
この記事を読みながら、「あ、うちもそうしてるかも」「これ、もうやってた!」と思った方もいるかもしれません。
それは、あなたがすでに無意識に “子どもの育ちを支える環境” を大切にしている証拠です。
環境づくりというと、「何かを変えなきゃ」と思いがちですが、すでに子どものために自然と工夫していたことが、しっかりと “第三の教師” としての役割を果たしているのです☺️
まずは、自分の中にあるこそ感覚を「ちゃんとできていたんだ」と認めてあげてくださいね。
そこからさらに「次にできること」が、きっと見えてくるはずです。
▶️次回は、子どもの成長を “評価する” のではなく、“記録して振り返る” というオーストラリアの「ドキュメンテーション」の考え方についてお届けします。
「観察」から始まる育ちの記録、一緒に深めていきましょう!
今日もみんなが笑顔で過ごせて
穏やかに熟睡できますように🩵

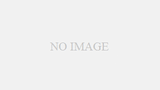
コメント