育児&幼児教育サポーターのUmiです😊
子どもたちを見ていると、こんな場面に出会うことがあります。
みんなで遊んでいる輪のそばに立っているけれど、声をかけられない子。
「仲間に入りたい」気持ちはあっても、それをどう表現すればいいか分からず、もじもじしている姿。
そんなとき、大人は「入れてって言えばいいのに」と思ってしまうかもしれません。
でも、実はその子なりに、心の中で一生懸命に葛藤しているのです。
♦︎「仲間に入れて」が言えない背景には?
子どもが「一緒に遊びたい」と思っていても、自分から声をかけられないことは珍しくありません。
それは、単なる“恥ずかしがり屋”というよりも、「断られたらどうしよう」という不安や恐れがあるからなのかも。。。
また、自分と他の子との関係性や、遊びのルールの理解がまだ不十分な場合もあります。
「今、話しかけても大丈夫かな?」と空気を読んでいたり、他者との距離感を測っていたり…。
そんな心の動きがあるからこそ、“仲間に入る”という行為は、子どもにとって大きな一歩です👣
この「つながりたい」という気持ちは、マズローの欲求段階説で言う“社会的欲求”にあたります。
人は、誰かと関わり、理解され、受け入れられることで安心し、自分らしさを発揮できるようになるのです。
♦︎ EYLFが大切にする「共同性」と「多様性」
オーストラリアの幼児教育において、こうした“つながる力”はとても大切にされています。
EYLF(Early Years Learning Framework)のOutcome 2では、以下のような姿が子どもの成長として挙げられています。
- 他者との関係の中で、自分の役割や立場を学ぶ
- 異なる文化的背景を持つ人々への理解や尊重を育む
- 協力・共有・交渉といった関わりのスキルを身につける
これは、「みんなと同じになること」ではなく、「一人ひとりの違いを認め合いながら、“つながりの中で自分を活かす”」ということ。
子どもたちは、日々の小さな関わりの中で、人との信頼関係や社会的スキルを少しずつ学んでいきます。
♦︎ 家庭でもできる「社会的なつながり」を育む工夫
こうした力は、保育園や幼稚園だけでなく、家庭でも丁寧に育むことができます。
たとえばこんな関わり方、意識してみませんか?
- 「ありがとう」「ごめんね」「どうぞ」など、やりとりの言葉を日常でたくさん使う
- 家族との会話に“相手の気持ち”を想像する問いかけを取り入れる(例:「おばあちゃん、喜んでくれたかな?」)
- 絵本や遊びを通して、いろんな人の視点に触れる機会を増やす
社会性は、正しさを教え込むのではなく、日々の関係性の中で“体験”を通じて育まれるものです。
だからこそ、うまくいかない日があっても気にしない!
子どもが人との関係の中でつまずいたとき、「大丈夫、一緒に考えようね」と寄り添うことが、いちばんの学びになります。
♦︎ つながることで、学びが深まる
子どもたちが安心して人と関わり、思いを伝え、受け取る経験を重ねていくこと。
それは、単なる“人付き合い”を超えて、子ども自身の「学ぶ力」を育てる大きな土台になります。
“つながりたい”という気持ちは、子どもたちが生きる力そのもの。
その気持ちを大切に育てていきたいですね🌿
最後まで読んでくださり、ありがとうございました😊
今日もみんなが笑顔で過ごせて
穏やかに熟睡できますように🩵

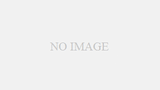
コメント